今回から新連載を始めます。
タイトルは、
です。
(part1)の本記事では、科学の立場から芸術を眺めることの意義を考えます。
本記事を読んでいただければ、
科学や芸術が人間にとってどういう意味をもつのか、
人類の歴史を俯瞰した時に科学と芸術はどう連動してきたのか、
などを考えるきっかけになり、様々な教養が身につきます。
昨今のグローバル時代には、科学と芸術は非常に重要な教養の代表格です。
深いテーマ設定ですが、ぜひサクッといきましょう!
Contents
【2021】科学と芸術の違い、共通点は?寺田寅彦の考えは?科学技術が西洋美術に与えた影響3選 (part1)
科学と芸術は似ている?寺田寅彦は「YES」、世間は「NO」
突然ですが、質問です。
科学と芸術って似てると思いますか?
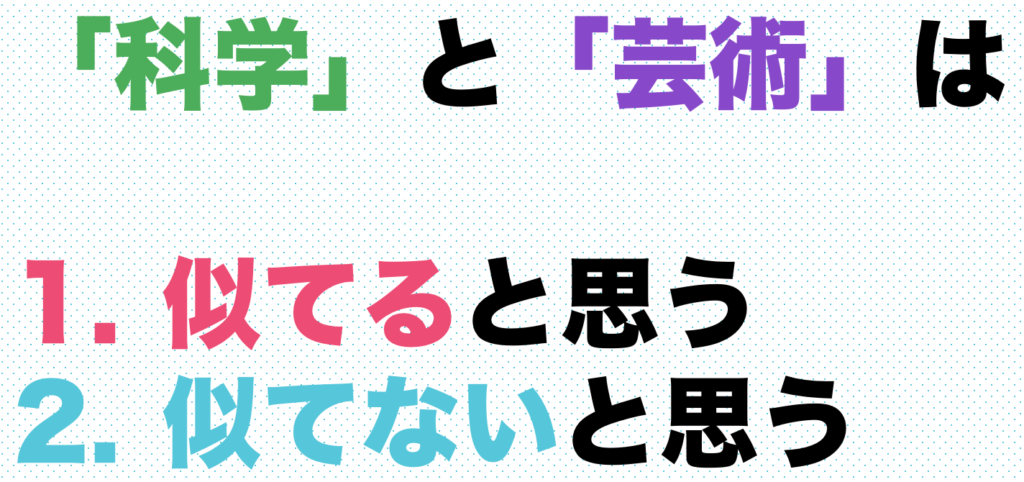
抽象的な問いですね。
人によって答えは違うと思います。
かの有名な物理学者・随筆家の寺田寅彦は、『科学者と芸術家』という本を著しました。
私ジャパナードは高校生の時に拝読し、非常に感銘を受けました。
この本を読む限り、寺田寅彦は「1.似てると思う」の立場をとるはずです。
しかし、世間的には「2.似てないと思う」の方が多数派なのではないでしょうか?

寺田寅彦の主張が気になる方は、青空文庫で無料でお読みいただけます。
ここでは、世間的な意見について考えてみましょう。

世間の目では、科学と芸術は正反対の性格を持っていると捉えられがちです。
科学は理性を、芸術は感性を重視します。
(科学者は実験で爆発するイメージで、岡本太郎は芸術で爆発するイメージですね笑)
この結果、
「科学」は科学の文脈で、
「芸術」は芸術の文脈で、
それぞれ別々に語られることが多いように思います。

しかし、寺田寅彦のように、科学と芸術の共通性を見抜いている人も大勢います。
ですから、科学と芸術の間を橋渡しする議論には、何かしらの意味が隠されているはずなのです。
そこで、本連載では、科学の文脈で芸術を語ってみたいと思います。

3つの科学的発明が西洋美術史を180度変えた
科学の中では、いくつかの偉大な発明が生み出されました。
世界の形を丸々変えてしまう発明も数多くありました。
その中でも、西洋美術史に多大な影響を与えた発明が3つあります。
の3つです。
皆さん、どれも一度は使ったことがありますよね?
これら3つの発明は、いずれも科学技術サイドの発明です。
では、この発明が西洋美術サイドに与えた影響とは、それぞれ具体的になんなのでしょうか?
皆さんも予想してみてください。

ヒントは、いずれも人間を「ある呪縛から解放した」という共通点をもつことです。
本記事の続き、こちらをクリック↓
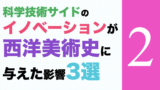
次に読むべき記事
無料・高画質で絵画を鑑賞するサイトはこちら↓

武蔵美の卒制展展示作品はこちら↓
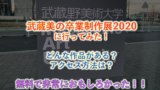
TOEFL100点をとった英語勉強法がこちら↓
英語はコツを知ってしまえば簡単に点数が上がります

このブログではpythonをはじめとしたプログラミングに関して、
どこよりもわかりやすく解説しています。
ぜひ他の記事もご覧になってみてください。


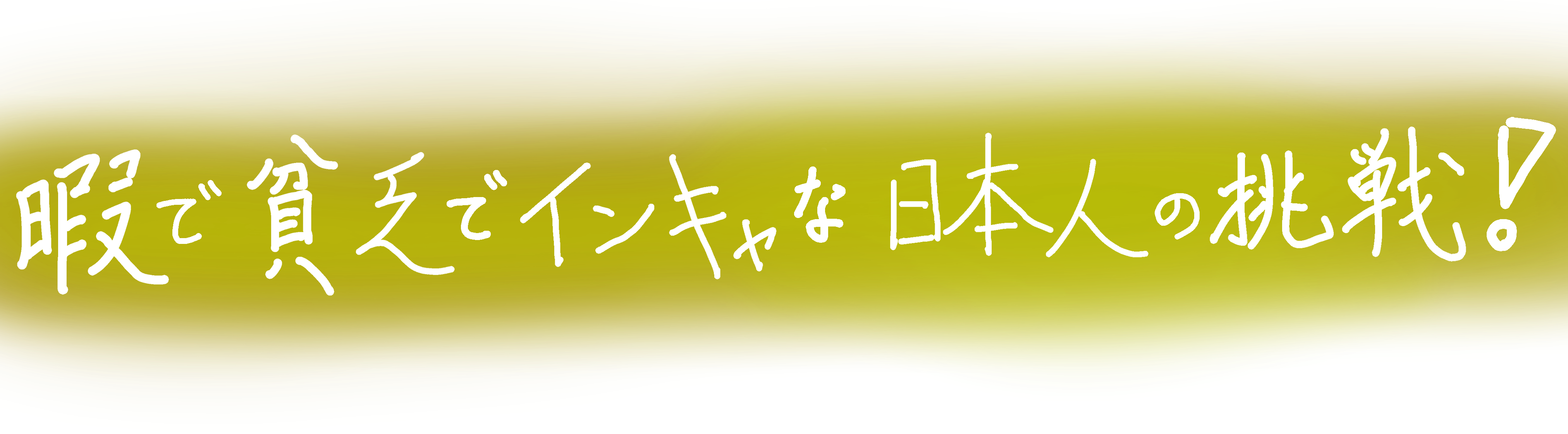
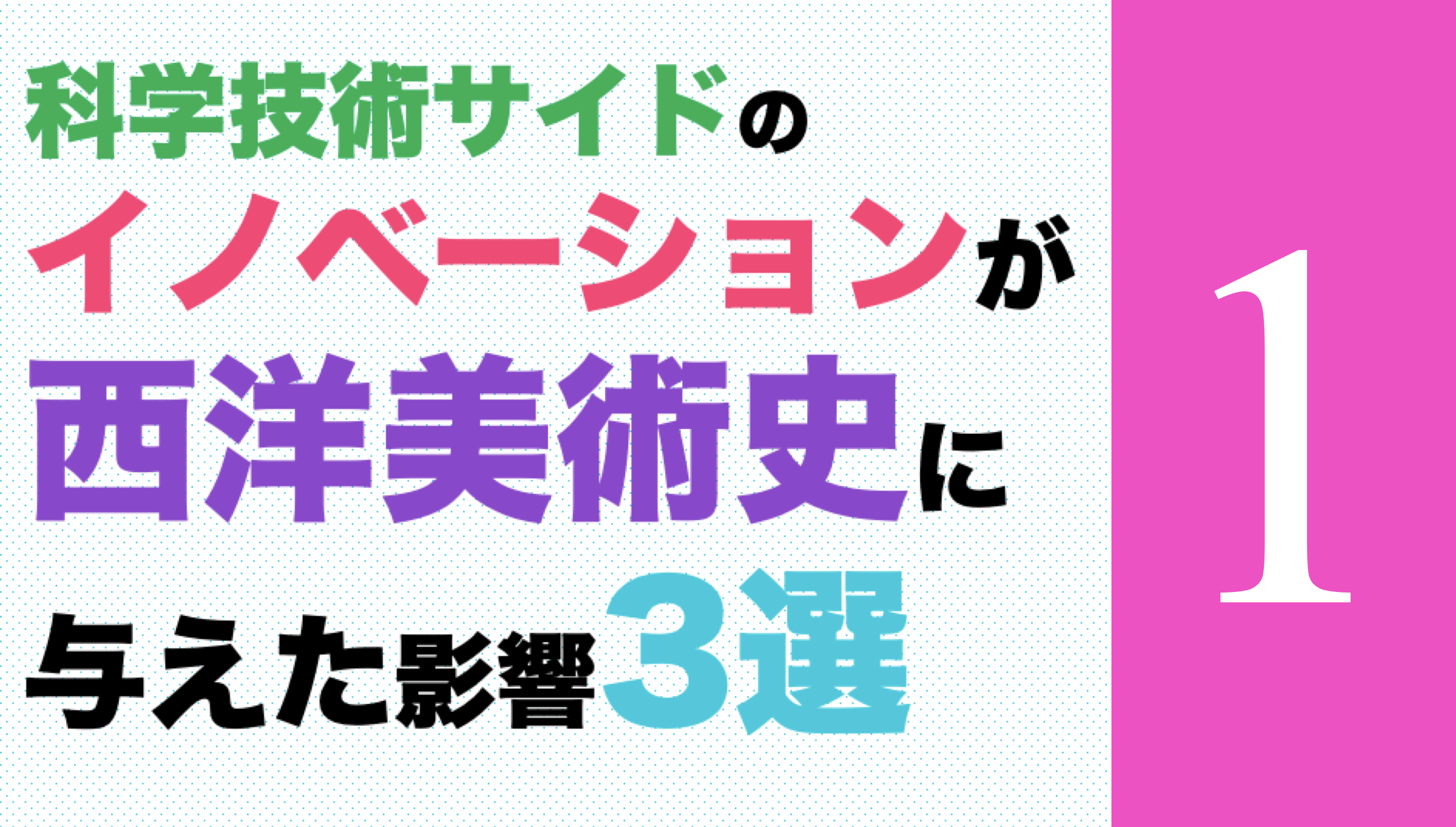
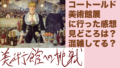

コメント